about

xocol(ショコル)の工房では、厳選されたカカオ豆を 自家焙煎し、石臼で挽いて チョコレートを作ります。 乳化剤や人工香料を使わず、油脂の追加もしない 自然なチョコレートです。
-----経営理念----------------------
ショコル
xocol STONE GROUND XOCOLATE
2013年10月 東京都世田谷区にてカカオ豆からチョコレートを作る工房を開始。
食材としてのカカオの可能性を追究。
FROM TOOL TO BAR
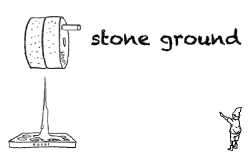
ものづくりは道具づくり。
素材の味を最大限に引き出すために。
ショコルが模索したのはカカオを挽く道具についてでした。
いくつかの試行錯誤を経て、道具とは、即ち作者の手であり、考えであると思いました。
ショコルの工房では昔ながらの石臼構造のものを使用しています。
カカオの香りを十分に残しながら、均一にきめ細かくペースト化。
いわゆるコンチングという作業はしていません。
言わばカカオ豆をそのまま頂くのと同然、素材の香りと味を最大限に保ちます。
材料はカカオ豆と砂糖だけ。
レシチンや香料、カカオバター等の余分な油脂分を添加する理由はありませんでした。
砂糖の粒子はつぶさずにそのまま残しています。
そうすることで、砂糖の甘みと食感、100%カカオのストレートな味わいと香りが、はじめて口の中で混ざり広がります。
x = c + s

xocol = cacao + sugar
チョコレートの歴史
チョコレートの原料となるカカオの発祥、起源や語源については諸説ある。
2018年11月に「Nature Ecology & Evolution」掲載された研究によると、今から5300年も前のエクアドル東南部の高原地帯にあるサンタアナラフロリダ遺跡のマヨチンチペ文明にてカカオのでんぷん粒の痕跡が見つかり、鐙型注口土器よりカカオは飲み物として摂取されていたと予測できるという。
その後の時代を築いてゆくマヤ族、アステカ族においては、語らずには始まらない程にその文化の中で非常に重要な作物となっていったカカオだが、ここでは詳しい記述はスキップしよう。
ショコルにとって最たる関心事である、今から約500年前にスペインのコンキスタドール(征服者)たちによってメキシコ征服が始まった年、 "1519年" に数字を合わせたい。
--------------------------
●ヨーロッパと産業革命
--------------------------
コンキスタドールたちにとって"豚にふさわしい飲み物" と表現されたものが、ヨーロッパにおいて "高貴な人々の飲み物・薬"となり、やがて固形へと姿を変えていったチョコレート。
まさに、カカオとの出会いから約300年もの間、それは裕福層と特権階級だけのためのものであった。
--------------------------
1519年、スペイン人によるメキシコ征服が始まる。
1828年、オランダ人のヴァン・ホウテンがカカオの脱脂とアルカリ処理を発明。イギリスの産業革命の波に乗りチョコレートの工業化が始まる。
1847年、イギリスのフライ社によりカカオ粉末とカカオバターを調合する製法が始まる。
1879年、スイスのルドルフ・リンツがコンチング法を発明。
1893年、アメリカではハーシーがメランジュール(撹拌機)設備を備えた巨大チョコレート工場を開始。同じ頃、ヨーローパではキャドバリー社、フライ社も同じように大量生産方式を導入し、安くて甘くておいしいチョコレートがようやく庶民の手に届くようになる。
--------------------------
●日本のあゆみ
--------------------------
1878年、日本初のチョコレートが両国若松屋より発売。
1918年、森永製菓がカカオ豆からの一貫生産を開始し徐々に日本国内に普及し始める。
1945年、戦後アメリカ製チョコレートが広まる。
1970年代には円相場が変動相場制になり1980年代にはバブル景気も後押しして日本人の渡航が急激に増加。大量生産型のチョコレートとはひと味違った丁寧なつくりのヨーロッパのチョコレート菓子も広く普及。
1990年代以降、アメリカを中心にカカオ豆からチョコレートまでを一貫製造する小規模メーカーが増加。製造工程においてクラフトマンシップ、または、スロウイーティングの精神に則ったものづくりが特徴。
--------------------------
産業革命以降は、まるでチョコレートが真の姿に戻るかのような歴史だったと言えよう。
しかし、それが本当に真の姿であるかどうかは分からないのだから、チョコレートは多くの人を惹きつけるのかも知れない。
*参考文献・出典:チョコレートの歴史 河出書房新社、Wikipedia、The New York Times
process
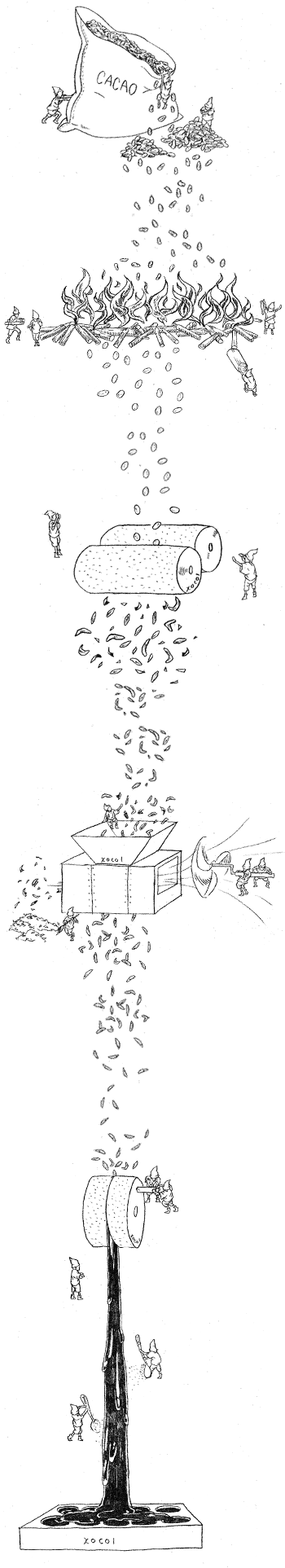
- Ⅰ カカオ豆を選別
- Ⅱ 焙煎 Ⅲ 粗く砕く
- Ⅳ 風選によりカカオ豆の殻を取除く
- Ⅴ 石臼で挽く
- Ⅵ 砂糖を入れ成型

